おすすめ宿泊プラン

【GW限定☆直前割】<素泊が最大3300円OFF> 南アルプス側or飯田市街眺望客室確約!天然温泉は最高の眺望
飯田城址の高台でお殿様・お姫様気分・・・当館基本の【素泊りプラン】が最大3,300円OFF! ☆21時以降はセルフチェックイン対応可能です。 電話にてお問い合わせください。『三宜亭 0265-24-0242』☆ ≪美人の湯、飯田城温泉かけ流し≫ アルカリ性でツルツル...
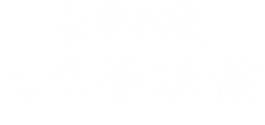


飯田城址の高台でお殿様・お姫様気分・・・当館基本の【素泊りプラン】が最大3,300円OFF! ☆21時以降はセルフチェックイン対応可能です。 電話にてお問い合わせください。『三宜亭 0265-24-0242』☆ ≪美人の湯、飯田城温泉かけ流し≫ アルカリ性でツルツル...